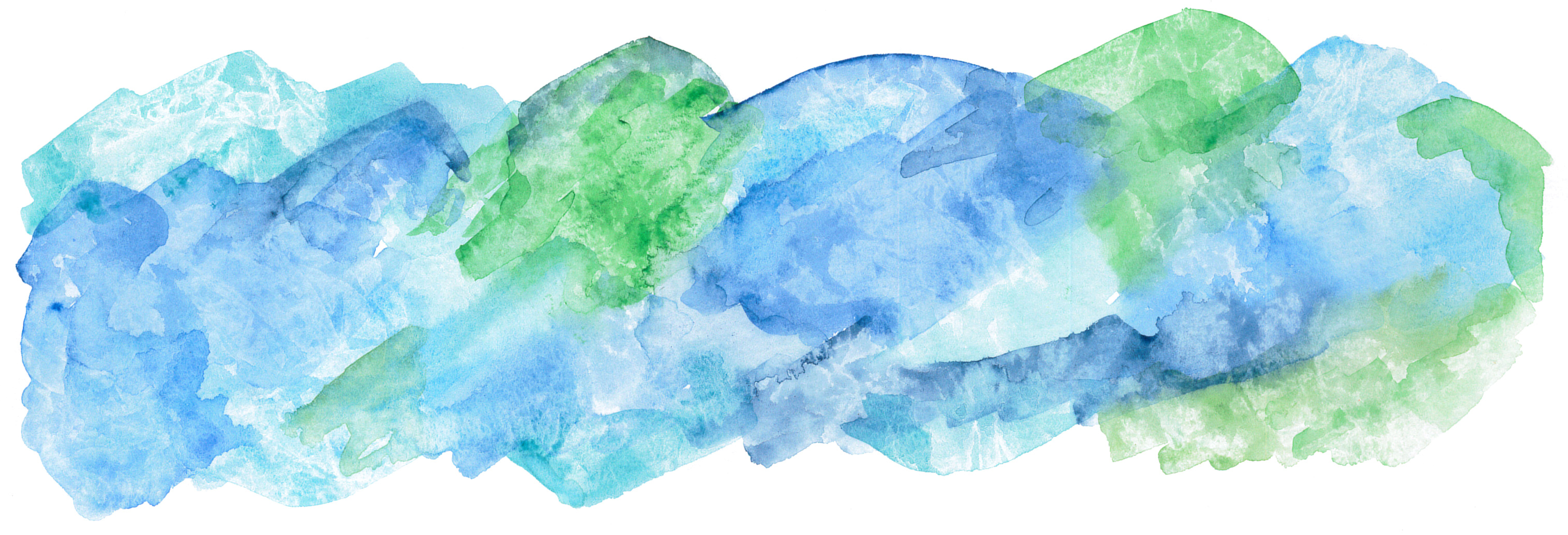Amika File 1

CM歌手面接から渡米まで
ゴキブリがゴキブリホイホイにかかった
Amika(5歳)詩ノート
もし人間ホイホイがあったら
エサは何がいいだろう
やっぱり お金かな
1996春
都内にある短大を卒業。在学中の前年から派遣社員として勤務していた某外資系銀行に入行する。
同年夏
インターネットで作曲家募集の掲示板に出会う。音楽の道に進みたい一念で無謀にも同行を退社… かたぎを捨てる。
1.
当時、株式会社ミュータント(広告音楽制作会社)代表の鈴木健士(当ファイルの筆者)は、習いたてのマッキントッシュで、インターネット位は覚えにゃ時勢に対応出来ん、といった中年管理職の強迫観念に取り憑かれ、日夜ひたすら雑多なホームページにアクセスしては役にも立たない知識を取り入れて独り悦に入っていた。
社員からすれば暇つぶしの道楽にしか見えず(事実 そうだった…)
何となく非難の眼がキツくなってきたので、多少なりとも会社の為に生かさねばと、とても軽い気持ちで様々な掲示板コーナーに「作曲家募集」の告知を出して体裁を整えてみたりした。
すると、動機を上回る反響があり、連日メールが 舞い込むことになった(その数30数名、そのうち3名が現在ミュータントにて修行中)。
そんな中で、○○○○銀行に勤める20才の女性からのメールは一際目立った。女性の作曲家は希少な上、しかも若いともなれば、広告会社やスポンサー受けも良いに違いない。
早速返事を書き、会う段取りを決めた。最初のキッカケは得てしてこの程度の、いい加減で適当、不純なものであったりする。
さて当日、約束の時間の30分前に最寄りの駅に着いた旨連絡が入り、懇切丁寧に当社までの道順を教えた。
どんなに遅くとも20分後には到着するだろうと待ちかまえていたのだが、約束の時間を過ぎても一向に現れない。
そうこうするうちに次の打ち合わせが入ったりして鈴木も忘れてしまっていた。
アポの時間から40分程すぎた頃、入り口に華奢で小さな、中学生の様な少女が立っていた。
あまりにも場違いなその姿に、まさかこの娘がくだんの女性とは思い至らなかった。
実のところ、電話の声の感じから多分太めの娘であろうと鈴木は思いこんでいた。声質が高めで響きが良い人は太っているに違いないという、根も葉もない滅茶苦茶な先入観からである。
真夏の外気を全身から発散させ、息も絶え絶えに彼女は自己紹介した。
茶色がかったちょっと長めの髪が汗で額に張り付いていた。
色素の薄いトパーズ色の瞳と、全く日焼けしていない白い肌に、鈴木はふと北欧の匂いを感じた。
これがそれから始まる現在までの神経衰弱のようなAmikaとのセッションの冒頭であり出会いである。
そして取りあえずその時わかったことは、Amikaは恐ろしく方向音痴であった。
2.
何はともあれ座らせ、面接を開始した。
「さて、今までどういった曲を書いてきたの?」
「曲を書いたことはありません」
「・・・・・・・・・・・・」
間違いなく作曲家募集と明記したはずだ。この娘は一体なにしに来たのだろう?
「私…歌が歌いたいんです」
「ああ・・・そう。じゃあデモテープ聞かせて」
「デモテープってなんですか?」
「いやあの、自分で歌っているテープとか持ってきてないの?」
「録ったことが無いんです、そういうの」
「・・・・・・・・・・・・」
ひょっとして業界憧れのシロートのお嬢さんを呼んでしまったのだろうか?
「あのね、一度自分の歌っているテープをどこかで録音してね、それから又いらっしゃい。ね?」諭すように言った。
すると、彼女はサッと立ち上がり、その場で英語の歌を歌いはじめた。
ベン・フォールズ・ファイブの「フィロソフィ」だった。
瞬間、社内の空気が止まった。
英語の発音、歌の表現力もさることながら、その大胆なまでの行動力と肝の太さ。これはとんでもない素材かも知れない。
作曲家募集の件などどこかに吹きとんでしまった。
鈴木は、彼女を育てることを決めた。それからは時間を忘れて話し込んだ。
頭の中で今後の計画を立てる。どんどん夢が広がっていく。
・・・よし、差し当たっては誰かコンビを組めるサウンド・プロデューサーを探そう・・。
それから3日後、Amikaから電話が入った。
「鈴木さん、私、あさってから3ヵ月ニューヨークに行ってきます!!」
「ニュ・・ニューヨーク?! さ・・3ヵ月!!??」
「鈴木さん、アメリカで勉強するといいって言ったじゃないですか」
「・・・・・・」
確かにそんなことを言ったような気もする。話の流れの中で。でも、まさか数日後に行くとは思わないじゃないですか・・・・。
Amikaは行動的である、というより、かなり無謀である。
「向こうに着いたらメールを入れます。まだ住むところを決めていないので」
「な、なにー!?」
Amikaは出会ったばかりでニューヨークに行ってしまった。○○○○銀行を辞めちゃって…
ニューヨークに旅立ってから3日後、メールが届いた。
その内容は一読して頭を抱え、読み返して心配になり、改めて考えて、まあこの距離じゃ何も出来ないことだし、取りあえず生きて帰ってこれればいいかと、こちらの気持ちをざわつかせるには充分な内容のものだった。
要約すると、
日本料理のレストランに貼ってあったアパートメントの広告を見て不動産屋に問い合わせ、安いし、まぁここでいいかと契約を決めようとしたところ、そこはジャンキーの巣のような所だと教えてくれた人がいてやめたとか、今夜は宿なしなので24時間営業の店で夜を明かしますとか、そんな内容である。
それから又、数日連絡が途絶え「死んだな・・・」と思いはじめた頃、第2信のメールが届いた。
音楽学校の夜間に短期入学したと書いてあった。
住むところがどうなったのかは分からないが、まあ何とかなったようではある。
ニューヨークには前からの友人もいたようで、鈴木が責任を感じて心配したほどのことはなさそうだ。
こうして帰国するまでの3ヵ月間、何度かメールが届いた。中にはホントにこのままでいいのだろうかという危なっかしい状態もあった様なのだが、適当にクリアしているみたいなので放っておいた。
帰国から歌詞制作開始

3.
3ヵ月のニューヨーク修行(?)を終えて、Amikaは帰国した。
久しぶりに会ったAmikaは、初めて会った時とは明らかに変わっていて、どことなく顔つきも締まってきたように思える。
もともと小動物的な趣があったのだが、言うならばおが屑の中をはい回っていたハムスターが、常に天敵の存在に脅かされる栗鼠に変身したというか・・・。
今時、ニューヨークにひとりで行って生活することなど、それほど珍しいことではない。
ただそれでも、自分ひとりで住むところを見つけ学校を選び、又ジャズクラブ等にも出入りし、気に入ったボーカルを見つけると師事をお願いしたりと、それなりに危ない目に遭いながらも、同郷人と群れることなく、その地での生活に溶け込もうとしてきたAmikaはなかなかどうして大したものだ。
上げ膳据え膳のタレントやアーティストが多い中で、自分の人生を切り拓いていけるこの行動力はいずれ大きな武器になるだろう・・・
でもマネージャーになる人は大変だろうな、とその時は他人ごとのように思っていた。
4.
「私は2月になったら詩を書き始めます」
1997年が静かにスタートして間もない1月の10日頃、Amikaは宣言ともつかない口調でぼそっと言った。
「何で2月なの? 今は書けないの?」
「・・・・・・・・・・」
まぁ、色々とテーマ探しとかあるんだろうなと理解を示し、詩に関しては時間を置くことにした。
差し当たってはAmikaに合った作曲家でも探そうかと考えたのだが、色々な作曲家のサンプル曲を聞かせても…「私じゃないような気がします」の一言でアッサリと捨てられる。
累々と作曲家の死骸が溜まりはじめた頃、Amikaは、一本のカセットを差し出した。
「私が今、いいなと思っているアーティストの曲をまとめてみました」
そのテープを聴いた印象を要約するならば、繊細でアコースティック、ジャージーでロンドンでスウェーディッシュ、多少狂気をはらんでいて、でもポップ。
目指している方向があるような無いような。
・・・結局何を作ったら良いのか分からなくなってしまったので、曲についてはしばらく考えないことにした。
5.
2月になった。
2月の3日に7編、4日に5編、5日に・・・10編。そんな調子で2月の中頃までに約50編程の詩がメールで送られてきた。
正直驚いた。
今までのストックを提出してきたのかと思い、質すと全て新作だと言う。
物量に圧倒されたのもさることながら、作品としての際だった存在感、そして独特の感性に驚かされた。
歌の詞としては全く定型が成されておらず、そのままメロディをのせることは出来ない。
いわばポエムなのだが、そんなことはどうでもいいやと思わせるオリジナルな表現力から、鮮烈にエンターテインメントを感じた。
出会ってからの半年間、アーティストとしての方向性を色々と探ってきたのに、何を提案しても本心から納得してくれず、なかなかスタートラインが見えなくてイライラしていた。
だが、Amikaが作る詩の世界がそれまでの試行錯誤を全て払拭してしまった。
本人から発せられるものが結局はそのアーティスト本人の羅針盤なのだと、とても当たり前のことだが、それを確信するに充分な作品群であった。
しかし、何で2月にこだわったのか、今もってナゾのままである。
因みにその時の詩を幾つか披露したい。
『ナンを食べにいく』
Amika
11時半 ナンが食べたくて
昼前から 時計を睨んで
今日が最後と昨日決めたのに
どうしてこんなに食べたいんだろう
インドに行けば?と友達は笑う
タイじゃ駄目なの?とみんなも笑う
笑えないほど カレーが食べたい
少し甘くて 出来立てで
あのナンの味 忘れられない
教えてくれた あの店には
明日からはもう行かない
夜は彼女といつも来てると
その言葉が耳に張りついてうるさい
12時前 ナンが食べたくて
この際辛口食べてみる
辛くて目が潤んでも
誰も気にしないあの席で
教えてくれた あの店には
明日からはもう行かない
夜は彼女といつも来てると
その言葉が耳に張りついてうるさい
混みすぎたら僕たちが困るから
誰にも教えないと言ってたのに
12時過ぎ ナンが食べたくて
財布片手に歩き出す
辛さで目が潤んでも
誰も気にしないあの店へ
『二人暮らし』
Amika
いい加減伸びた前髪を
切るか伸ばすか決めさせてあげる
あなたの趣味で
長い長い時間をかけて
やっと二人で寝れるようになったけど
たまにはキザになることを
忘れないでいて欲しい
それぞれが持つ本棚や
服のたたみかた 違う育ち方
来た手紙の数 争って
ゴミの車を二人で追いかけて
そんな風に暮らしていきましょう
長い長い時間をかけて
やっと二人で暮らせるようになったけど
たまにはマメだったあのころの
あなたに戻って来て欲しい
小人がいつか 増えたとしても
名前で呼び合う このままで
『とかげ』
Amika
とかげは目つきがすごく悪くて
とかげは見た目が 皮っぽくて
とかげは 尻尾が切れても逃げる
友達には なれない動物
できれば 近寄りたくもない
夢の中で あなたはとかげで
あたしの愛する あなたはとかげで
あたしはあなたを育てていました
餌をやり 水浴びをさせてみたり
たまには なでてあげました
私の愛する あなたがとかげなら
仕方がないから それさえ愛そう
そう決めて あなたを育てました
止まり木つかんで 動かないまま
柵越しに 何を思っているのか
聞いてもわかってない様子
あなたの家を 掃除して
土も新しいものに換えたら
少しは穏やかな目になりました
これは夢で あなたはとかげで
柵に時々体当たりしてる
またあたしのこと 睨むから
あなたを外に出してみた
芝生の向こうの 広い木陰が
何だかとても嬉しそうで
あたしも一緒に嬉しくなった
そのうち日が暮れてきて
うたた寝してたら あなたは消えてた
すると何だか泣けてきて
気がつくと もう朝が来ていた
変わらぬ朝 変わらないあたし
目を覚ますため シャワーを浴びても
言葉が何も なかった分だけ
とかげのあの目が離れない
あなたがいなくならないように
あなたを 放し飼いにすると決めた
冷蔵庫開けるあなたの腕
見上げながら言葉を交わす
あたしが思う全てのことを
あなたにはわかるはずもない

作詞から出会い、散文まで
『入れ物の中』
Amika
私たちは皮膚という入れ物の中で
こぼれそうなものを抱えて生きている
何とかやっていけそうに思えたり
どうにもならないように思えたり
いくら退屈だと口にしてみても
真実味を持たないように思えるのは
私たちが皮膚という入れ物の中で
液体でも個体でもない
見えないものを抱えているからだ
6.
3月、やけくそになりそうなほどにたくさんの詩を抱えて呆然とし始めた頃、随分とご無沙汰だった人が訪ねてきた。
高野寛クンとの仕事で出会った藤沢氏である。
以前はオフィス・インテンツィオという会社の人だったのだが、今は違う会社でプロデューサーをしているという。
その日は「中村一義」という新人のプロモーションでやってきた。
一聴するに歌詞にしても歌にしても、とにかく枠にはまりきらないスケールのデカさを感じた。いやはや凄い新人が出てきたものだと感心してしまった。
そして、このアーティストを発掘しマネージメントしているファイブ ディーという会社にもとても興味が湧いた。
「藤沢さん。実は僕も今、一人デビューさせたいと思っているヤツが居るんだけれども…」
(ホントは聴いてくれる? と言いたいところなんだが、何せ詩ばっかりで曲は無い)
「へぇ、どういうの、聴かせて?」と、藤沢氏。
「いや、まだね、曲は聴かせられる状態じゃ無いんだけれどね」
(状態どころか影も形もない)
「いや、なかなかね、詩がいいのよ」
苦し紛れにそう言って、Eメールからプリントアウトしただけの、まとまっていない詩の束を藤沢氏に渡した。
藤沢氏は半ば社交辞令で言ってしまった言葉を後悔している様だった。
束だけを見ればうんざりしてしまうほどの量である。
やれやれといった表情で諦めて作業に取りかかった。
一枚読んでは脇にふせ、全部読んだ後に又、ふせてあったモノをひっくり返し、最初の方のモノを引っぱり出して今度は時間をかけて丁寧に読み直す…しばらくの間、無言でその作業を続け、最後の一枚を脇にふせるとトントンと束を揃えて差し出した。
「鈴木さんこれコピーとって。見せたい人が居るので」
「どうですかね。いけそうかな」
藤沢氏は眼鏡の奥の、ちょいと垂れ気味だが優しい目を鈴木に向けるとスッと視線を外した。
「詩だけじゃ分からない。でもなんか凄味があるよね…」
「・・・・・・」
「うちの社長…佐藤剛に見せたいんだ」
この時、藤沢氏がたまたま、しばらくぶりで鈴木に会いに来なければ、その後のAmikaの人生も若干変わっていたかも知れない。いや、大きく変わっていたかも知れない。分からないけど・・・。
そんな事があったとは全く知らず、Amikaは相変わらず詩を書き続けていた。
よくぞこれだけテーマが見つけられるものだと、感心を越えて呆れるほどである。しかし、その内容はやがて抽象度を増し、内面的になっていった。
同時に短い散文が増えてくる。
見なければならないものから必死に、むしろ意図的に視線を逸らそうとしてる…。
散文.1
Amika
『ホームの絵』
こっちを向く人
きりりとした顔
心に残る目
きれいな耳たぶ
強すぎる口元
はねた毛先
横にいるのに話そうとしない
空はオレンジ
もうすぐ紺色
ごみ箱はいつも口を開け
鏡はいつも見る人を待つ
散文.2
Amika
『黙々を生きる 』
肉体と精神は相対するものでしょうか
どちらも改良と忘却を繰り返し
野心と空虚を合わせ持ち
焦燥感と衝動をばねに
怠慢からの覚醒を心待ちに
容赦なく降り積もる悔恨に怯え
勘当したはずの迷いの狭間で
連帯に憧れ嘲笑を恐れ
虚栄と挫折と沈黙を嫌い
触覚を信じ無知を振りかざす
そんなことはどうでもいいのです
ただ黙々を生きるだけです
このような散文詩が、毎朝メールボックスを開く度に怒涛の様に鈴木の頭の中に飛び込んでくるのである。
このまま書かせるべきか、しばらく止めさせるべきか・・・。
Amikaが地下鉄のプラットホームで何両もの電車をやり過ごしながら、ため息をついている情景が浮かんでくる。ちょっとヤバイかもしれない・・・。
Amikaの中で何かが起きている…。
7.
そして、まもなくAmikaは、ふっと書くのを止めてしまった。まるで蚕が狂ったように桑の葉っぱを喰い、大量のフンをひねり出し、いきなり繭玉にくるまれて眠ってしまうが如く、それは唐突にやってきた。
「鈴木さん・・なんか・・書けなくなっちゃいました。なんにも見えないんです」
言葉を選びながら鈴木は慰めるように言った。
「うん・・。書けないときは書く必要はないよ。書きたくなったら又書けばいいさ」
「ちがうの・・。書きたいんですホントは!!・・・でもね、書けば書くほど自分が壊れていくのが判るんです。壊れていく自分と向き合わなければならなくなるのがもうイヤなんです!!」
最後の方は絞り出すような声だった。
そして、これから半年、Amikaからは一遍の詩も出てこなかった。

停滞期
8.
Amikaは詩が書けなくなってしまったと同時に、音楽を主体とした表現活動からも離れていこうとしているようだった。
鈴木は出来れば年内中に協力者を見つけ、Amikaのプロジェクトを作り上げたいと考えていたので、ちょっと、いや、かなりの焦りを感じていた。
「書きたくなければ書かなくても良い」などと言いながら、実は会う度に様々な手段でプレッシャーをかけ続けた。
ビクターからデビューしたロック系の女の子のライブに連れて行っては、「早くAmikaのライブが観たいものだ。でも今のままじゃ詩の朗読会しか出来ねぇな」と、冷たい視線で言ってみたり…。
その当時デビューした新人の女性ボーカルのCDを集めて聞かせては、「もたもたしとらんで早く我々もCD 作らにゃあかんがね」などと、無茶苦茶な方言で言ってみたり・・・。
その度にAmikaが視線を宙に漂わせながらため息をついていたのを、鈴木はあろうことか見落としてしまっていた。
この時期のことについては、若干注釈を加えたい。
実は、この『Amika FILE』を書くに当たってこの辺りのことをどう記すべきか、結構悩んでしまった。
Amikaとも話し合いを持った。彼女は開口一番こう言った。
「やめましょうよ。なんでそんなことまで書く必要があるんですか」ケンもほろろであった。
「作ったもの以外、特に見せるものなんて無いでしょう」
僕もその通りだと思う。
実際Amikaは、Amikaが作り出す表現物だけで充分エンターテインメント出来るアーティストだ。余計なキャプションは要らない。
それでも書いておこうと決めたのには理由がある。
多分Amikaのデビューシングルになるであろう『ふたつのこころ』。
実はこの曲が生まれた背景にはこの時期のAmikaの心理状態が密接に関係している。
何も書くことが出来なくなったAmikaが半年ぶりに僕に出してきた詩がこの『ふたつのこころ』の原型に当たるものだった。
そして、この曲こそ、Amikaがアーティストとして初めて認められ、現在のAmikaプロジェクトの強力なスタッフィングにつながる礎になった記念すべき曲なのである。
本人がどう思っているかは関係なく僕はこの曲がAmikaの「アイデンティティソング」だと信じている。
世の中に、人を励ますための音楽、いわゆる応援歌はたくさん存在するが、この曲はちょっと違う。
今のAmikaに、人を励まそうなどという余裕は全くないし、そんなおこがましいことは彼女自身カケラも思っていないだろう。
あくまでも自分に対する決意表明だと受け取っている。
何かを目指すに当たって、というよりは生きている上に於いて、本当に信じられるものは自分しかないし、逆にどこまで自分を信じられるかが実はとても大事なことであったりする。
それでも時には頭で考えていることを心が理解できないことはあるし、心が求めていることを頭が否定してしまうことはある。
どんなにポジティブに生きたいと思っていても体がいうことを聞かなかったり、頭の中ではこんなことではいけないと分かっていながら感情がそれと逆の方向に向いてしまう。
とても単純なことなのだが、そのふたつのバランスが一緒になったとき目指すべき方向や、生き方が見えてくる。
この詩を読んだ時に僕は・・ああ、何はともあれ抜けたな・・・、と思ったのである。
この詩が出来上がった当時、Amikaをとりまく状況は決して今のような順風満帆といえるものでは無かった。
レコード会社もマネージメントも決まっていない、まさに宙ぶらりんの状態だった。
だが、この詩を見て、そして曲に合わせた時、本末転倒も甚だしいが、デビュー出来なくてもまぁいいか、と思ってしまった。
本当に心底ホッとしたものだった。
そんなわけで、僕としてはこの時期のAmikaのことを伝えずに避けて通るわけにはいかない。
何とも注釈が長くなってしまったが、そんなわけでストーリーに戻っていく。
9.
そして、或夜、Amikaを車で家まで送って行った時のことである。
街道沿いのファミレスで、遅い晩飯を摂っていた。
特になんてことのないとりとめのない話をしていたつもりだったが、いきなりAmikaは泣き出した。
しかも涙をこぼすなんて生やさしいものではなく、絞るような声で(!?)…。
深夜のファミレスで、泣き出す若い娘と、いわゆるオッサン…。
援助交際のもつれ…もしくはサラ金の厳しい取り立て…。
好奇の視線が四方から突き刺さってくる。
なだめることも出来ず、アワワと周りを見回す鈴木。
あまりにもいきなりだったので、何がどうなったのかも分からずあたふたとして、仕方が無いのでトイレに逃げてしまった。
用を足しながら鈴木は自分の胸に問いかけてみた。
今までの会話の中で何か彼女を傷つけるようなことを言ってしまっただろうか?
・・・特に思い当たるフシはない。
・・・まあ、強いて言うなら最近少し追い詰め過ぎたかもしれない。
・・・とりあえず謝っておくか。いや、でももっと違う理由かもしれないし、例えばハラでも痛かったとか・・・そりゃないな。
・・・でもどうせ泣くなら車の中にしてくれりゃあいいのに何でこんなところで泣くんだ、クソ!しまいに腹が立ってきたりして。
席に戻ると、少し落ち着いたのかAmikaは泣き腫らした目で外を眺めていた。
何を見るでもなく、焦点は定まっていない。
しばらく沈黙が続いた。コーヒーカップが空になり、ウエイトレスがポットを手にお代わりを聞きに来た。
するとまた泣き出した。
ウエイトレスは、一瞬立ちすくむと他のテーブルに行ってしまった。後ろ姿の肩が小刻みに震えている。
さすがにもう逃げる訳にはいかないので、鈴木はAmikaに話し掛けた。
「何か・・あったか? 」
「・・・・・・・」
Amikaは何も言わない。
「俺が言ったことで何か傷付いてしまったとか・・・」
Amikaは首をただ横にふる。
「まあ、何があったかはわからんけれど…」
「ちょっと黙ってて下さい」
「ハイ…」
とりつくしまがない。
結局この日はこのまま訳が分からずAmikaを家まで送って行った。
車から降りる時にAmikaは一言「すみませんでした」と言うと、顔も上げずにドアを閉めた。
鈴木は車を走らせバックミラーから遠去かるAmikaをみつめていた。曲がった杭の様に立ちつくすAmikaを見ながら、…死にゃしないだろうなと、ついとんでもないことを考えてしまった。
1997年5月、まだ1曲も出来あがっていないというのに。

10.
それからしばらくの間、Amikaは泣くか、視点の定まらない目でボーッとしていることが多くなった。即興でもデタラメでもいいので、何かしら前進できる作業をしなければと、スタジオに入れてみたが… 無駄だった。
何も出来上がらないばかりか、一人にして欲しいと言われ、鈴木は追い出されて鍵を閉められてしまった。お手上げである。
このまま無理遣りに何かをしようとすれば全てを壊してしまいそうだった。結局、時間をおくしか方法は無かった。
しばらく会うのを止めた。
ただし、全くの没交渉になってしまうのは何やら嫌な予感がしたので、3日に一度は電話連絡を課した。
それすらも嫌な時はEメールを出すようにと言い、約1ヵ月間ほど顔を合わせることはなかった。
7月半ば、Amikaに初めて会ってから1年が過ぎようとしていた。
唐突に・・明日会えますか・・・というEメールが届いた。
その時、鈴木は実はちょっとドキドキした。
音楽的な話やアーティスト活動に関する話はまだ時期尚早だ、できるだけ避けねばならん、よし、映画でも観に行こう。
何を見るかは決めずに、恵比寿のガーデンプレイスで待ち合わせをし、上映時間が迫っていたので殆ど話もせず、そして何の予備知識も持たずに映画館に入った。
始まった映画はキャロル・キングをモデルにした、バキバキの音楽物サクセス・ストーリーだった。
「アチャーッ」と思ったがもう遅い。
隣のAmikaが気になって仕方がなかったが、逆にこれで楽しめるようならばもう大丈夫かもしれないという一種の賭けのような気持ちで最後まで観た。
長い映画だった。
終わってからティー・ラウンジに入り、ようやく落ちついて話をした。
「映画、面白かったです。でも…なんか遠い世界ですね…」とAmika。
「いや、別にそういう意味でこの映画にしたわけではなくて、その…いや、たまたま…」しどろもどろの鈴木。
「いえ、いいんです。ありがとうございました。最近は少しは眠れるようになったし、もう大丈夫だと思います。ご心配をお掛けしました」
目の下に隈を作りながらそう言われても額面通りには受け取れない。
実は何が原因でAmikaがこのような状態になってしまったのか、漠然とではあったが、何度かのEメールのやりとりや電話で聞かされていた。それはひとつのことではなく、色々なことが複合的に絡み合っていた。
Amikaとの関わりについて鈴木には基本姿勢があった。言いたくないことは聞かない。特にプライベートに関しては、本人が話すこと以外には興味を持つことを避けてきた。鈴木にとっては内容よりも状態が重要であった。
したがって詳しいことについては、Amikaは今に至るまで明言してはいない。
が、どうやら家族から、音楽活動を模索するための猶予期限を設定されていたようだ。それが二十歳の誕生日からの2年間、すなわち98年の2月3日まで。現在は7月なので、残りあと7ヵ月、もうわずか7ヵ月である。
具体的には、その時点でハッキリとした展望、つまりはレコード会社との契約が実施、もしくは決定されていなければ、容赦なくかたぎの職業に戻らなければならない、というものらしいのだ。
まあ、親にしてみれば当然のことである。やくざな稼業ではあるし…。
レコード会社を決めることが特にそれほど難しいとは思えなかった。
ただし、Amikaについては出来ればトップ・プライオリティで出発点を決めたかった。そしてそれが出来うる才能を有する素材だと鈴木は確信していた。
ところが、現段階でプレゼンテーション出来るものは歌詞にもなっていないポエムだけである。少なくとも曲をつけてアーティスト・パワーを訴求できるだけのデモテープを作らなければならない。
実は、この時点でAmikaが心密かに考えていたのは、作曲についても自分で行うというもの、いわゆるシンガー・ソングライターでありたいということだった。
今でこそなんら異論を挟む必要のないこととして受け入れられているAmikaの自作だが、その当時は「ヒョエ~ッ」である。なにせ作ったことが無いんだから。
さて、そうしたギャップの中で、Amikaは…。
――確かに自分が書いてきた作品に対し、鈴木は高い評価を与えてくれている。
でも果たして他の人達はどう思うのか。
(当時、鈴木は人に見せたときの評価を一切Amikaには伝えていなかった。
Amika自身は自分の作品を、自分から生み出されたものとしてとても大事に思っている。
だがそれが即、音楽ビジネスの中でキチンとした評価を得られるものなのか。
具体的な展望が立てられない現状の中で唯一存在している詩でさえも、Amikaの心の中では不安材料としてくすぶっていたのだった。
この時期、鈴木はAmikaがどんなに不安そうにしていても、何に対してもただ「大丈夫」「ノープロブレム」「ドントウォーリー」としか言わなかった気がする。
何の裏付けもないくせに・・・。
そしてもうひとつ、自分が楽器を全く弾けないことや音楽理論を知らないことを、音楽を表現する上でとても非常識なことだとAmikaは考えていた。
ごく親しい周囲の人達からもそれらの点を指摘されて、ひどく落ち込んでいたのである。
曰く「コード進行も知らなけりゃ、譜面も読めないヤツが音楽の道に進めると思っていること事体が無謀だ」と。
鈴木は何度も、そんなことは別に大した問題ではない、自分もそんな理論なんざ全く分かってないことも含めて説いたものだが、Amikaは聞く耳を持たなかった。
当時のAmikaをとりまく環境、その時の音楽的なレベル、そして、それらをクリアせねばならない時間が刻一刻と迫っていることなどが原因となって、Amikaはバランスを崩してしまったようだ。
唯一側にいる鈴木は脳天気にも「大丈夫」としか言わないし・・・。
しかしマイッタ。1997年7月、いきなりあと7ヵ月!!
おそらく、ひとつひとつのことはこんな文章で片づけられるほど単純ではなかったのかもしれない。
とにかく鈴木は、Amikaのその時の状態があまりにも痛々しかったので、原因を追究して潰していくよりもまずは、以前のAmikaに戻ってくれる方法を最優先で模索することにした。
第一に、現在の状況や作品をどんなに親しい友だちであっても話してはいけないし見せてもいけないと厳命した。
鈴木がどれだけ高い評価を下したとしても、鈴木が本当に信頼できる人なのかどうか、Amikaにとってこの時点では判じ難い。
それよりはむしろ、永年つきあってきた友人達の評価が気になるし、上位に立ってしまう。鈴木にしてみればこの状況はとても厄介だった。
なぜなら、これはいい!!と評価した作品を、次に会った時にAmikaは平気で捨ててしまうのである。
そこで、まずは周囲からノイズを徹底的に排除したのだった。
それは友だちのみならず、ミュータントのスタッフにも及んだ。
どんなに善意の評価であっても、時期によってはプロデューサーにとって、両刃の剣になってしまう場合もある。
その上で、今まで以上に信頼関係を強固にするため、出来うる限りAmikaと話をする時間を増やした。
Amikaが抱く全ての疑問に対して、とにかく納得するまで何時間でも何日でも話を続けた。
しかし、納得してくれたかなと思って別れると、翌朝やたらと長いEメールが届いていて、前日のディベートが徒労に終わったことを悟らされることもしばしばであった。
時には何時間も無言のまま、ただクルマを走らせているといったこともあった。
鈴木が話し掛けると「黙ってて欲しいんです」と言われ、仕方なくカーステレオのスイッチを入れると、何も言わずにいきなり切られる。音を耳に入れたくなかった様なのだが…。
鈴木にとっては一種の拷問であった。
・・・ホント、あの空間と時間は今思い返しても胃の裏の辺りが張りつめてくる気がする。
その頃のAmikaの、あの焦点の定まらない、宙を見つめる目を鈴木は忘れることが出来ない。
ところで、それからずいぶん経ってから(現在でも)、Amikaはあの目でぼーっとしている時がある。やばいなと思って訊く。
「どうした。何か言いたいことがあったら言えよ」
「えっ…いやーおなかすいちゃって・・力が入んなくて…」
ひょっとするとあの時もただ腹が減っていただけだったりして…。
それからはまず、モノを喰わせることがプロデュースの基本になった。
・・・・・閑話休題・・・・・

作曲開始
11.
刻々と迫り来る、かたぎに戻らねばならないシンデレラ時間に具体的に対処するべく、そして楽器なんか弾けなくてもコードなど知らなくてもメロディは作れることを証明するため、実際にスタジオに入って実践する時が来た。
鈴木も悠揚と構えているわけにはいかなくなってきたのである。
そう、時間がないのだ。そのために強力な助っ人をキャスティングした。
現在、続行されているAmikaのレコーディングで、殆どの曲のサウンド・プロデュースを担当している「たつのすけ」氏である。
彼は、仲井戸麗市氏率いるチャボバンドで、キーボードとアレンジを担当している。その人となりについては追々説明していく。
いや、しないかもしれない。何せ時間がない…。
取りあえず現在のAmikaにとっては、なくてはならない人であるとだけ記しておく。
まず、今までの膨大な詩の中から録音する素材を選んだ。
一番最初に取り上げたのはな・な・なんと!!「ナンを食べにいく」であった。
失礼。つまらんシャレをかましている場合ではない。時間がないのだ!!
まず最初にAmikaが持っているこの詩についての音楽的イメージを聞く。
ジャンル的なことからテンポ感、グルーブなど。そして、そのイメージに近いコード進行をたつのすけ氏がピアノで弾いていく。
もしも、Amikaのイメージと違っていたときは再度コード進行を探っていく。
最初のうちはAmikaもなかなか自分のイメージを上手く伝えられず苦しんでいたが、段々と見えてきたのか、おおまかなコードが決まった。
その上でAmikaがコード進行に従ってメロディを乗せていく。
その間、DATテープを録音しっぱなしの状態にしておく。
作業を続けていくうちに、魅力的なメロディがふっと現れる。
その瞬間、テープを止めて3人で聞き、良ければそのメロディの先を作っていく。
いわゆるバンド形式の作曲方法である。
Amikaの詩は、作った時にはメロディのことはあまり考えられていない。
字数は一応揃えてあるが、帳尻が合わなくなる部分も出てくる。
そうした部分については宿題にしておき、とにかく大体の曲の構成を作り上げてゆく。
こうして、セッションを繰り返すうちに曲が仕上がっていくというわけである。
さて、なかなか良い曲が仕上がった。
「出来たじゃあないの」
「鈴木さんこの曲好きですか?」
「うん、ポップでいいんじゃないの」
「…そうですか」
そうは簡単に事が進まないのがAmikaプロジェクトである。
翌日・・・開口一番Amikaが言う。
「うちに帰って聞いてみたけれど、何か違うんですよね」
「・・・・なにが」むっとして言う。
一日8時間近くかけて作り上げたものをいきなり壊そうとするこいつはナニ?
「古くさいっていうか…」
「ほー」ヒクヒク…。
またイチからやり直しである。
とにかく自分が納得するまでAmikaは徹底的に人を引きずり回す。
まあ、この頃は慣れてきたけれども。
そんな風に3歩進んでは2歩半下がるという作業が始まった。
それでも何とか、ジリッジリッとではあるが、プロジェクトは前進し始めた。
鈴木はこの作業を“だるまさんが転んだ方式”と名付けた。
進みながらも、いつ繋いだ手が切られるかと、スリルだけはたっぷりとある。
そして、この作業によって生まれたのが、「ナンを食べにいく」、「ビール」の2曲だ。
ある日、Amikaは人から借りたギターを使って自分で曲を作って来た。
コードも知らなけりゃ弾いたこともないギターの音を探りつつ作ったその曲を、テープで聞かされたのだが…正直なところ、よく分からなかった。
おそらくチューニングも合ってなかっただろうし、ちゃんと弦を押さえられていないので音がびびってしまって…。
でも、ここでボロクソに言ってしまうと繋いだ手を切られてしまいそうなので・・・取りあえず評価は先に延ばした。
それでも、Amikaが自分一人で一から曲を作ろうとし始めたことを、鈴木は見逃すわけにはいかなかった。
早速スタジオに入って、今度はたつのすけ氏の力を借りずに、しかも何も楽器を持たずに新たな曲作りに挑んだ。
詩は「How can I say」。
この曲を作るときにAmikaと話をしたのは、とにかく素直でわかりやすいメロディにしよう、ということである。
例えば唱歌の持つ郷愁感。でも絶対に暗いのはダメ。
なにせいきなり「例えば私が今死んでしまったら」などという歌詞から始まるのだから。
とにかくいつものようにDATテープを回しっぱなしにしながら、Amikaは歌い始めた。
コード楽器なしでのアカペラ作曲作業は、ハタから見たらとてもシュールだったと思う。
たまにメロディに詰まると鈴木が提案する。
「そこはじゃあ、こういうメロディにしてみようよ」
すかさずAmikaが返す。
「それ、強烈にダサイと思います」
(ぐっ・・・・)
「じゃ…じゃあこういうのは」
鈴木がまた他のメロディを口ずさむ。
「なんか、昔の歌謡曲みたいで…ちょっと」
「・・・・・」
鈴木は…お、大人だ。とにかく徹頭徹尾、Amikaは一切、他人のメロディを認めようとはしないのだ。
まあ、鈴木のメロディも別に大したもんじゃあございませんけどね。
ブツブツ・・・。
いじけながらも作業を続けているうちに、「How can I say」をAmikaは全くの独力で完成させた。
その後Amikaがひと息ついたところで、保留にしていたギターで作ったという曲を、試しにアカペラで歌わせてみた。
・・・あれっ・・・、なんか印象が違う。結構いい!
「いいじゃん、この曲も完成させようよ」
こうして「オレンジの匂い」が生まれた。
10月、なんとか先が見えてきた。
あと4ヵ月。

デモ制作とファイブディー
12.
このようにして生まれた曲を11月に入ってデモテープとして録音することになった。
当初はバンド形態で、ある程度きっちりと構成を決めてやろうと思ったのだが、まずはAmikaというアーティストのキャラクターを、出来る限り生の状態で感じて貰うことが重要だと考え、きわめてシンプルな構成に変更した。
そんなわけで、たつのすけ氏のピアノ一本で録音することになった。この録音自体は意外にすんなりと終わってしまったのでそれほどのドラマはない。
11月初旬、デモテープ4曲完成。あと3ヵ月。
ファイブ ディーの藤沢さんとはその後しばらく会っていなかった。
以前に詩のコピーを渡した後で何度かは会っていたのだが、特に新たな展開がなかったので、まずはデモテープが出来たら、ということになっていたのである。
さて何をおいても藤沢氏に聞いて貰わねばと思い、電話をしたところ、彼はレコーディングでロンドンに行っているという。しかも12月の末まで。
取りあえず帰ってくるのを待つしか無いなと思い、マーケティングも兼ねて他の人達に聞いて貰うことにした。
最終的にはその人達とは組むことはなかったのでここでは名前は出さないが、幾つかのレコード会社や音楽出版社からはかなり良い感触が得られた。
評判は上々といったところである。
Amikaのマネージメントに関して鈴木は、はじめから他社に預けるつもりでいた。
理由は簡単。
鈴木はマネージメントについてはプロではない。
そして、Amikaのプロジェクトをより強力に、且つ磐石にしたいので、その方面のプロフェッショナルと組みたいと考えたからである。
以前そのことについて藤沢氏に相談した際に、「検討は出来ると思います」という返事をもらっていたので、とにかくマネージメントに関してはファイブ ディー、1社に絞り込むことにした。
社長の佐藤剛さんとは、別件も含めて鈴木は何度か会っていたのだが、その時から何となく、この会社とAmikaの相性が良さそうに思えた。
それもひとつの要因だった。
やはり藤沢氏の帰国を待つしか無いのかなと諦めかけた頃、ロンドンから電話が入った。
「自分はこんな状態なので聞けないが、大筋は社長の佐藤に繋いであるので、直接彼に聞いてもらった上で判断を仰いでほしい」と。
そんな訳で早速テープを送ったところ、直ちに佐藤剛さんから「会いませんか」と言う電話を貰った。
それが11月19日のことだったのだが、何と佐藤剛さんも21日にはロンドンへ出発してしまうのだという。
ここでも時間がない!翌日すぐに、Amikaを連れてファイブ ディーに出向いた。
「とても良いと思います」にまっと笑って佐藤剛さんは言った。
「詩だけ読ませて頂いて、とても気に入っていたのですが、正直、曲をつけるのは難しいと思っていました。でも自分でこれだけいい曲を作れるのであれば、何の問題もないでしょう」
これで決まりか!?
「でもあと少し、決め手になる曲を聴いてみたいですね」
やはり、それほど甘くはない。
「僕はこれからロンドンに行って、年末にいったん戻りますが、すぐに正月からブラジルへ行きます。でも、1月の半ば頃には帰ってきます。その時までに、是非」
良いけれどもウチではやらない、と言うのはよくある話だ。
つまり、次回に聞かせる曲が事実上の最終プレゼンになるということだ。
1月の半ばというと、Amikaに課せられている期限まで、もうわずか2週間しかない。もし、それで駄目だったら…さあどうしよう…。
いよいよ最後の正念場がやってきた。
13.
実をいうと鈴木の中では、これだ!という曲がすでにあった。
その曲は、以前にたつのすけ氏との作業で出来かかっていたのだが、詩とメロディーのマッチングがどうもしっくり来ないらしく、Amikaが保留にしていたものだった。
ファイブ ディー からの帰り道、Amikaと話をした。
「あの曲しかないな」
「でも詩がないですよ」
「今までの詩の中から選ぶしかないんじゃないか」
「う~ん、なんかそれ嫌です」
「じゃあ、新しいの書けるか?」
「多分大丈夫だと思います。書きます。ちょうど今、出かかってきてる時期なんです」
曲自体にはとても力があって、シングル向きだなと、鈴木は思っていた。とにかく、曲に負けない歌詞さえできれば…。
ところが――。
それから年が明けても、Amikaから歌詞は上がってこなかった。
段々とあせってくる。
しかし、ここまで来るともう鈴木も手の差しのべようがない。
ただただ待つのみである。
とはいえ苛々はつのる。
そこで、サウンド作りに気持ちを集中することにした。
Amikaは、自分の作品や、声質を表現するためのサウンドにも徹底的にこだわった。
曲の感じからするとデジタル・サウンドではなく、アナログが良いのではないか、というのがAmikaと鈴木の一致した意見である。
そこで多少リスキーではあったが、思い切って生音で録音することを決めた。
デモテープなので、リズムについては生音ドラムの打ち込みループでも事は足りるのだが、いずれ本番の録音を行うことを踏まえて、この機会にAmikaに合ったレコーディングの方向性を見極めてみたいと思ったのである。
更にセッションの方法についても、アレンジャー主導の流れ作業というか、事務的スタイルではなく、Amikaの意志が重視されるスタイルをとることにした。
すなわち、スタジオミュージシャンを起用しないこと。
アレンジについても簡単な進行とコードだけを決めて、後は現場の雰囲気とAmikaの歌の説得力でミュージシャンを引っ張っていくという方法。
Amikaとミュージシャン同士の相性も大事だし、何よりもAmikaが先頭に立つことが重要である。
そうして、たつのすけ氏とも話をした上で、最終的にドラム、ベース、ギターの3リズム構成という、最もシンプルな形態でいくことにした。

デビューが決まる
14.
さて、舞台は整った。
後はAmikaの歌詞だけである。
録音が4日後に迫った1月の13日。
その日は、Amikaから上がって来た歌詞をメロディに合わせ、録音前の最終確認をする予定にしていた。
が、歌詞が上がってこなければシャレにもならない。
そこへ、なんとも晴れ晴れとした顔のAmikaが入ってきた。
遂に出来なくて開き直ったか・・・。
「どうかな ?」
「・・・・・」
何も言わずにバッグからフロッピーディスクを取り出すと、Amikaはマッキントッシュの前に座り、起動させた画面をプリントアウトし始めた。
レーザーノイズが一行一行を印字していく。
どうやら出来上がってはいるようだ。
しかし問題は中身である。
プリントアウトされた歌詞を無言で鈴木に渡し、横に座った。
読み始める。Amikaはその間、天井を見ながら、とてもちいさな声でソフィー・ゼルマーニの歌を口ずさんでいる。
鈴木は心の中で、歌詞を メロディに合わせて歌ってみる。
・・・ああ、そうか。
染み込むようにAmikaの気持ちが伝わってきた。
そして、Amikaの目を見ながら、淡々とした口調で言った。
「出来たじゃない」
「はい。出来ました」
15.
長い半年間だった。
そして、何かと濃い半年間だった。
タイトルは「ふたつのこころ」と書いてあった。
そんなわけで、取りあえずここで『Amika FILE』の第一部が終わります。
この時の「ふたつのこころ」のデモテープが最終的なキッカケとなり、その後ドラスティックな展開がAmikaに起こるわけです。
家族との約束も果たせました。
なんと、ぎりぎり2月の3日、まさにAmikaの22歳の誕生日のその日に、全てが決まったのでした。
そして、Amikaにとっては間違いなく最高にして最強の方々が、スタッフになってくれました。
ファイブ ディーの佐藤剛さんをボスに仰ぎ、インターブレンドの赤羽社長。
ディスクガレージの中西社長。
フェイスA&R の田村社長。
社長ばっかりのまるでタニマチ状態。
Amikaも、もう腹を減らすことはなさそうです。
そして、インターブレンドの江口さん、レコード会社バリアフリーの中村さん、田村さん。ファイブ ディーの小寺さん。
1月の20日に最終決定を頂いて、わずか1ヵ月もしないうちにこの陣容です。
そして、3月3日からは一気にアルバムのレコーディングがスタートしたのです。
1年半に渡る神経衰弱もようやく実を結び、これからは僕一人ではなくみんなでAmikaに振り回されるかと思うと…まるで洗濯機の様なプロジェクトが完成したわけです。
ここまで読んでいただいてもおわかり頂けるように、Amikaはなんともドラマになるアーティストです。
スリルもあるし、サスペンスもあるし・・・。
実際にはこれからがAmikaストーリーの始まりであって、これまでのことは序章に過ぎません。
(私、本当にデビューできるかどうかまだ半信半疑です。ひょっとしたら死んじゃうかもしれないし・・・。などと、相変わらずAmikaは恐ろしいことを、しらっとした顔で僕に言います。)
「いやー、売れませんでしたー」では、このAmika FILEは、とてもとても「さむい」ことになりかねません。
そんなわけで、「触らぬ神に…」じゃなかった「継続は力なり」という言葉をAmikaと私も含めたスタッフご一同様に贈りつけて、まずは第一部の終わりとさせていただきます。
1998年6月 鈴木健士
追:そして・・・レコーディング。これがまたいろいろとあって、ドラマなんだ。さすがはAmika。振り回す、振り回す。
to be continued
『ふたつのこころ』
Amika『ふたつのこころ』
考えずにページをめくるこの指先も
よくできたカメラのように動くこの目も
時々自分のものかどうかわからなくなる
だけど他の誰のものでもない
この薄い皮の下には血が流れていて
図鑑で見た通りに絶えず動いてる
まるで体と頭に心はふたつあるように
壊れるまで続くことを知ってる
悲しみはいつか麻痺していくことを
悲しみの中でもわかるように
自信がない日も見失う時もいつでも
磁石が指すように求める場所にはたどり着ける
ふたつの心でいつも強く願うなら
家までの階段を駆け上がるこの足も
電話が鳴る音に気がつくこの耳も
ぜんまいであたしたちは動いてる訳じゃないから
本当に願うことを知ってる
自由になることに憧れていたけど
生まれた日から自由だった
もう駄目だと思う日も迷えるときも
磁石が指すように求めている場所を見つけられる
ふたつの心がそれを強く願うなら
誰かがそばにいてもなぜかさみしかった
やさしい言葉も届かない場所にただうずくまって
いたなら歩くこともできない そうでしょう?
自信がない日も見失う時もいつでも
磁石が指すように求める場所にはたどり着ける
ふたつの心がそれを強く願うなら
あとがき:AmikaFile 公開にあたって
この『Amika File』で書かれているデビューから、私は7枚のマキシシングルと2枚のアルバムをリリースして、体調を崩しレコード会社を辞め、しばらく療養生活を送りました。
それから2枚目のアルバムの編曲を担当してくれていた作曲家の夫と結婚し、15年以上CM音楽制作の分野で歌手&作詞家として活動を続けて現在にいたります。
途中マキシシングルを少し作ったりライブをやったりしましたが、このコロナ渦でなかなかライブ活動を再開できないため、今はYouTubeに以前の楽曲をアップしたり、新曲を作ったりしています。
鈴木氏を偲ぶ会では、久しぶりに当時携わってくださっていた方々と再会しました。
時間がぎゅっと縮み、プロジェクトを通して共に過ごした濃い時間を思い出し、胸が熱くなりました。
鈴木氏に天国から再び縁を結んでいただいた気がします。
今回この『Amika File』を公開するにあたり、鈴木氏のご遺族や会社の方々と連絡を取り、ご快諾いただきました。
当時は「こんなこと書かなくても」と思っていましたが、今となっては亡き鈴木氏が書いてくださった、私のデビューまでのプロフィールです。
音楽プロデューサー鈴木氏とご遺族の皆様、制作会社ミュータントの皆様方、
当時のFive-DやFaith Music Entertainment、ポニーキャニオンや東芝EMIの皆様、当時から今に至るまでライブでも組んでくださっているたつのすけさん。
次のリリースにあたり編曲を担当してくれる(であろう)夫と、
長らく私の楽曲を聴いて下さっている方々や、新しく出会ってくださった多くの方々に多大な感謝を述べてこの長いページを終わらせていただきます。
Amika
あ、そういえば。
このあと、実はAmika File2もあるのです。
どこかで公表していたそうなのですが、私は最近知りました。
鈴木さん、こんなことまで書いていたのかと。。
それでも記録してくださっていたこと、今ではなつかしくありがたいです。
もしよろしかったら読んでみてください。